Na_o_kiさんから投稿いただいた「私の英語学習法」です。
英語は学生時代から苦手ではありませんでしたが、社会人になって、会社の語学力向上の方針に乗っかる形で再び勉強を始めました。
今では大体TOEICで650点から700点はコンスタントに取れるようになりました。
そんな私の英語勉強法についてご紹介します。
英語で大変なのは、まずは英語耳を作ること。
なるべくたくさんの英文が聞き取れるようになることです。
単語が分からない上に、英語を母国語とする人の話す英語はとても速く、聴き取れるようになるまでが一苦労です。
ディクテーション
私が行ったヒアリング力向上対策は、ディクテーションです。
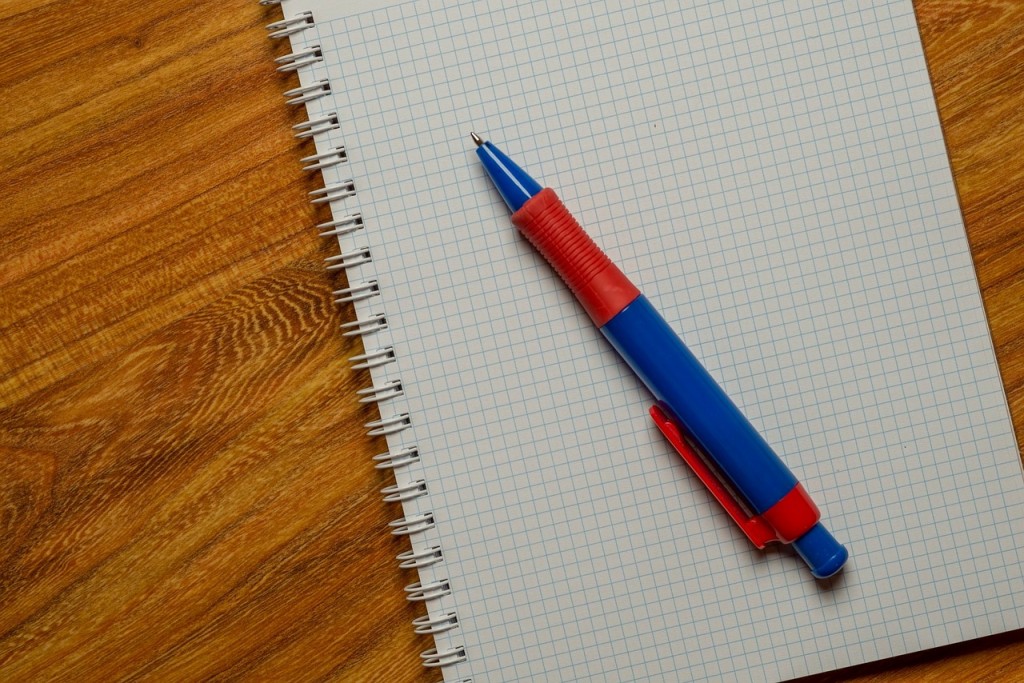
英語のCDを1センテンスごとに聴き取りながら、紙に書きだしていく作業です。
はじめはなかなか聞き取れないため、同じ部分を何度も繰り返し聴くことになると思います。
しかし慣れてくると、ある程度の長さの英文が聞き取れるようになり、繰り返し聴く回数も減ってきます。
ALCの「ヒアリングマラソン中級コース」
ディクテーションと並行してALCの「ヒアリングマラソン中級コース」も実践しました。
CD6枚、テキスト6冊、月次テスト6回分を半年かけてこなしていきます。
半年、特に飽きることもなく続けることができました。
中級コースなら自分の実力程度と考えていましたがなかなか難しく、全て完全に聞き取れるということはありませんでした。
しかし、7~8割聞き取れていたので、全体で何を言わんとしているのかは理解できたと思います。
シャドウイング
次におすすめなのが、シャドウイングです。コスモピア社の「多聴多読マガジン」を利用しました。

これは、英語を母国語とする人々の幼児レベルから社会人レベルまでの文章が掲載されていてCDがついています。
CDを聴きながらCDの音声を追いかける形で音読を行う、いわゆるシャドーイングを推奨する月刊誌です。
確かに、幼児レベル、小中学生レベルの英語であれば、読んだだけで瞬間的に意味が理解できるため、英語を生で理解するということが実感できました。
英単語の暗記(ボキャビル)
それから欠かせないのが単語の暗記です。
私は「英単語が面白いほど記憶できる法」という本を利用しました。
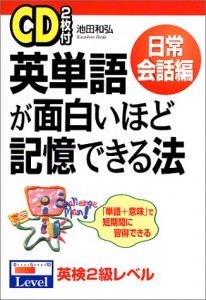
池田 和弘
CD付で、英単語のすぐ後に日本語の意味が流れる仕組みで、レッド赤、ブルー青というように英語と日本語をセットで覚えてしまおうというCDです。
これも何回も繰り返し聴いているうちに覚えられる単語が増えてきました。
いろいろと実践してきましたが、全体を通して思うことは、英語はまずは音読することが大事だということです。
音読することで、英語独特のテンポが次第に身についてきます。
また、部分的に分からない箇所があったとしても、そこを気にせずに先に読むことで全体としての意味が分かるようになり、分からなかった部分も気にならなくなってきますので、音読をお勧めします。
あとは継続は力なりです。
一か月や二か月では英語学習の効果は現れませんので、気長に継続的に行うようにしましょう。
ペンネーム:Na_o_ki(40代前半男性)
英語レベル:TOEIC700点レベル
社員の英語力向上を方針として勧めている会社は最近多くなっているみたいですね。
Na_o_kiさんは、大手のソフトウェア開発部門に勤務されているということなので、英語の文献を読まなければいけなかったり、海外との仕事など実務でも英語力は必要なのかもしれませんね。
時代の流れとして、英語力がますます求められている気がします。
今回の投稿とても具体的な学習方法の紹介で、僕もすごく参考になりました。
ディクテーションは、英語力が高い人はかなりの確率で学習経験があるという印象です。
僕はやったことがないので一度やってみたいと思います。
ALC(アルク)のヒアリングマラソンは有名ですね。当サイトの英語教材データベースでも紹介しています。
という3つのコースが用意されています。
またシャドウィングで使用されたという多聴多読マガジン。
定期購読をするか、コスモピア社のオンラインショップでバックナンバーを個別で購入できるみたいです。
多聴多読マガジンバックナンバー一覧
雑誌形式のものと、電子版もあるみたいですね。
Na_o_kiさん、ご投稿いただきありがとうございました。
- 目標:資格取得
- 資格・試験:TOEIC(L&R)
- 分野:リーディング(読解力) | リスニング(聞き取り力)
- 場所・ツール:教科書・参考書 | 通信系の英語教材
- 英語学習法:シャドーイング | ディクテーション | ボキャビル・語彙増強
- 英語レベル:中級
みんなの英語勉強体験談検索
全体験談数114個
The Japan Times Alpha(ジャパンタイムズアルファ) あらゆるレベルの人に購読をオススメする英字新聞です
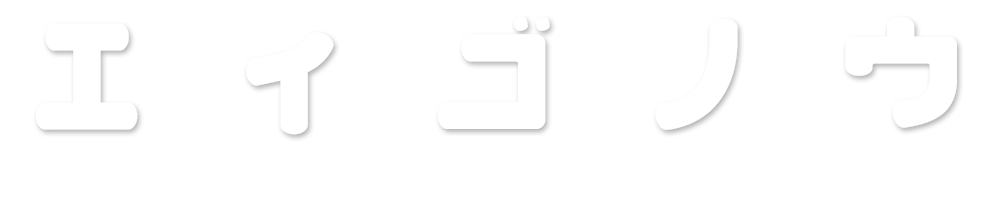
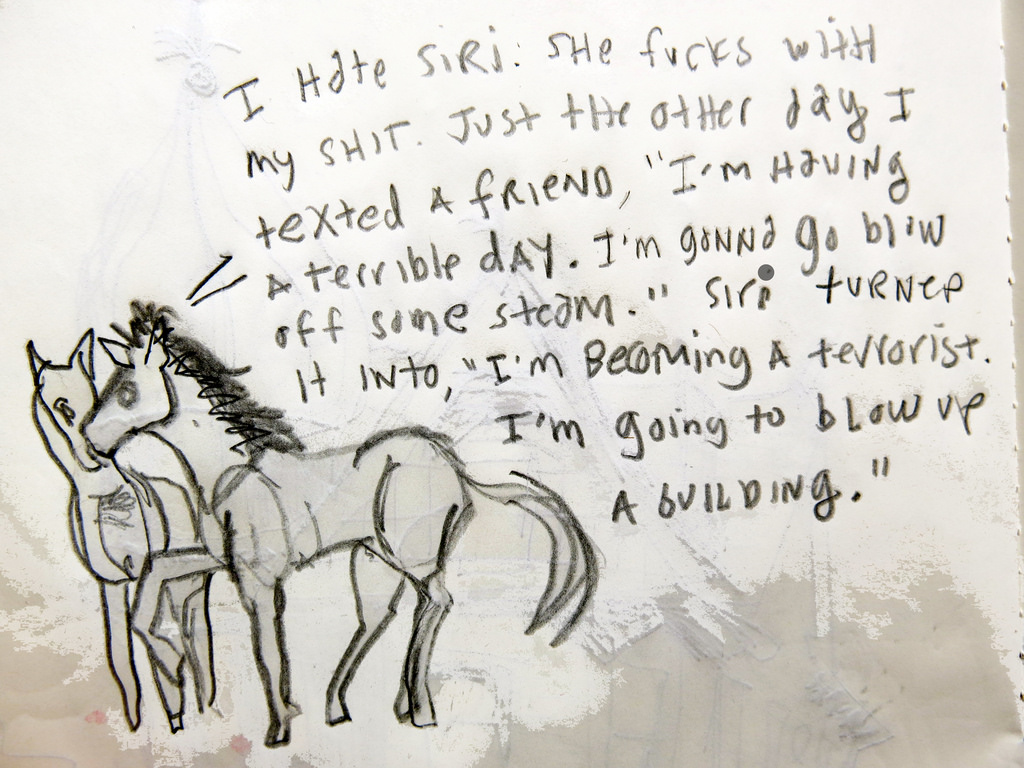



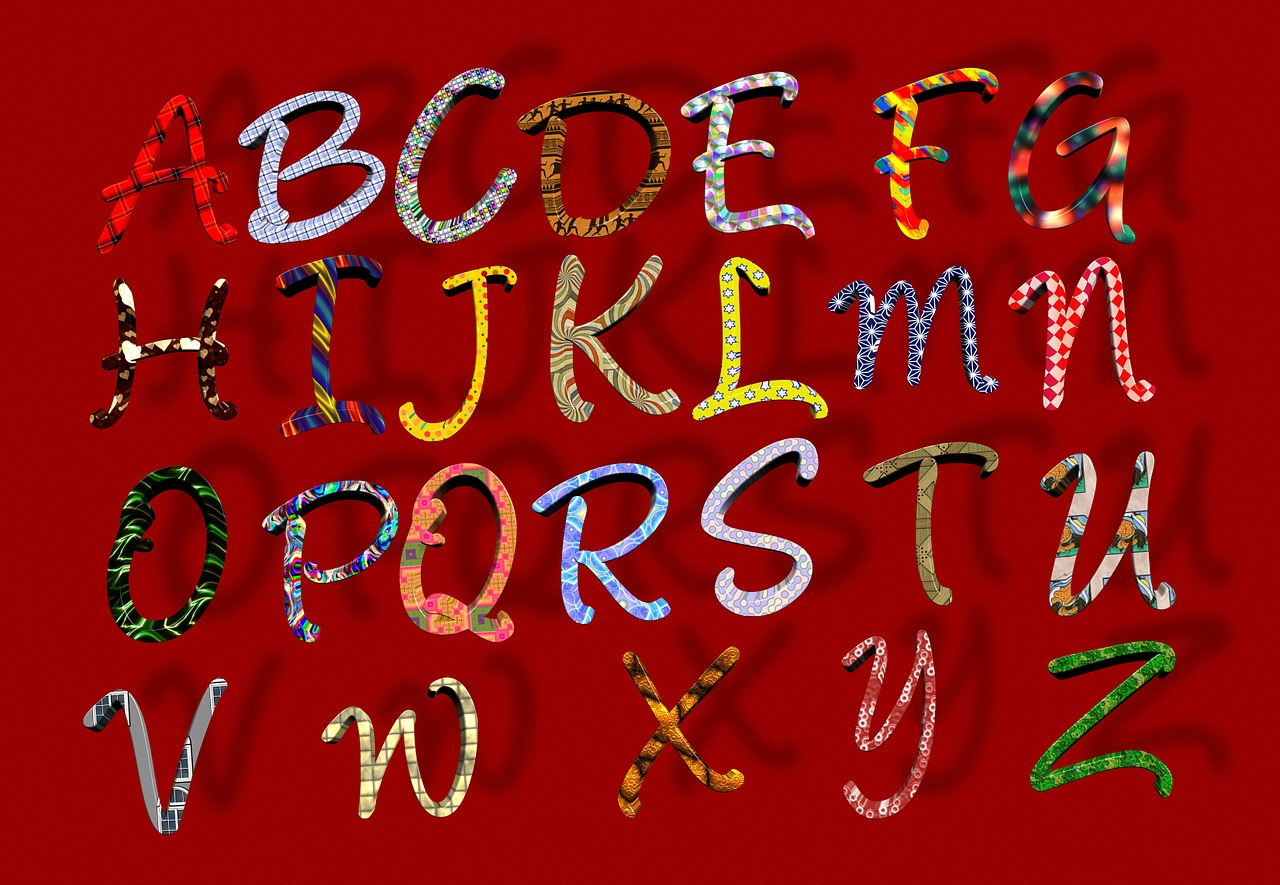
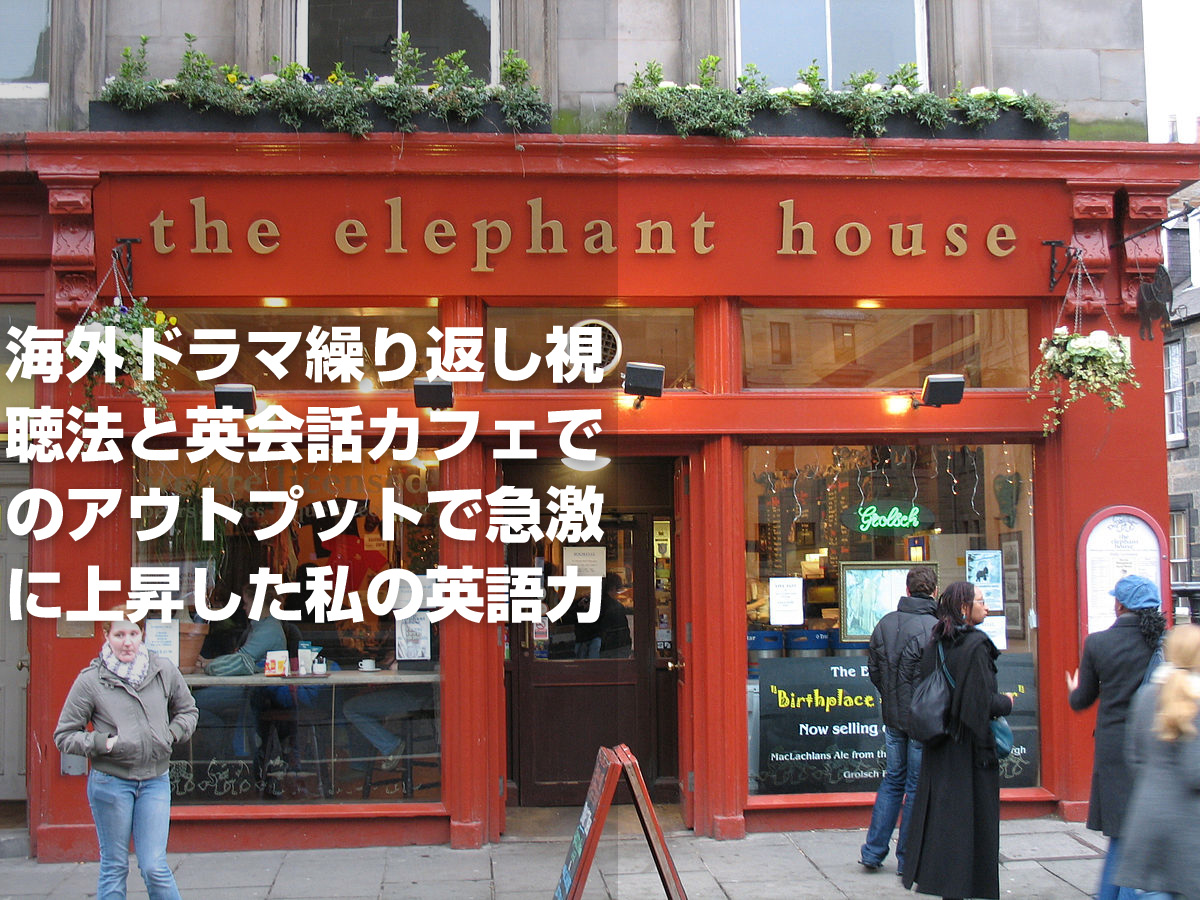
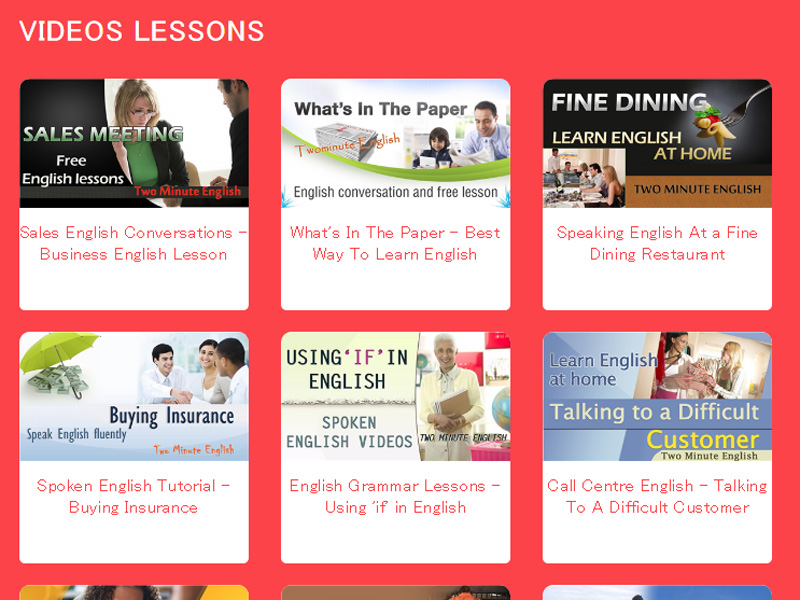

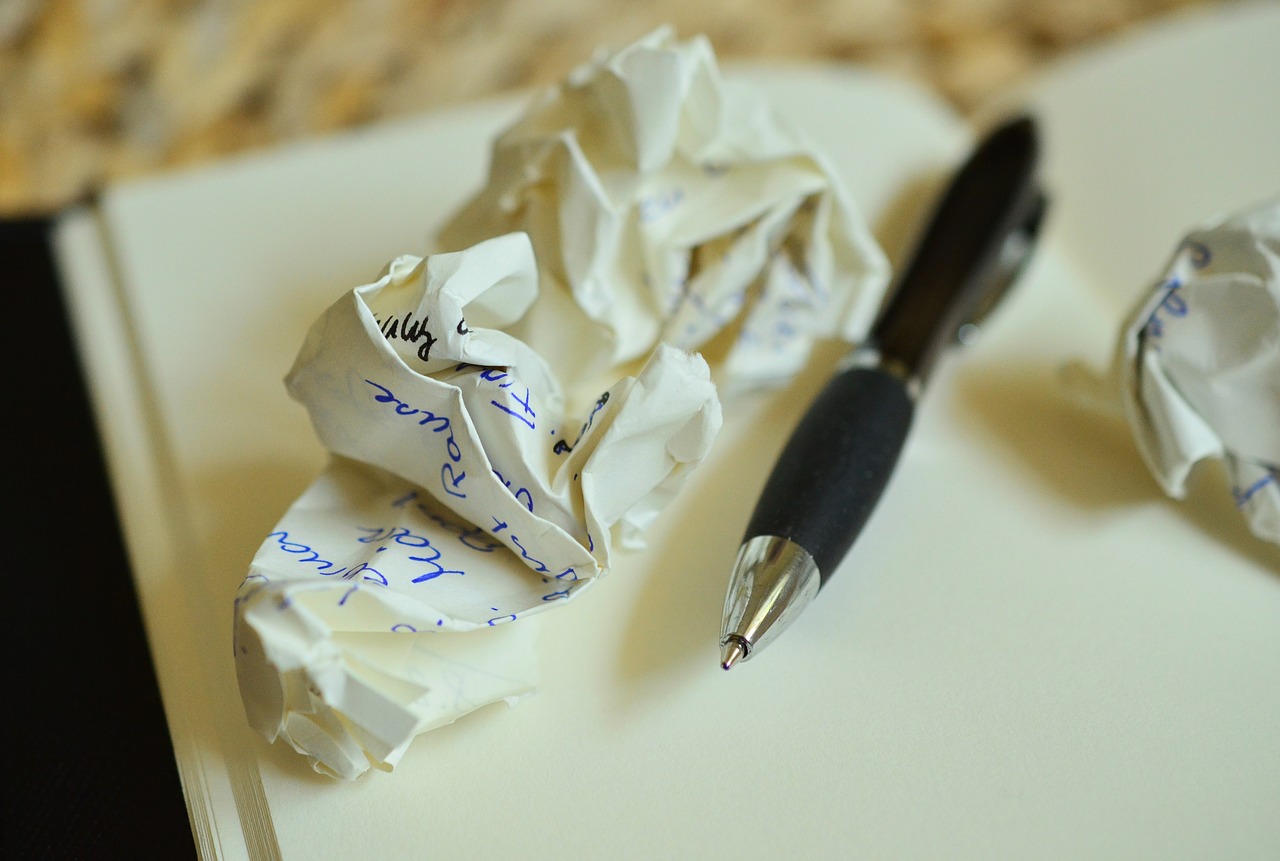

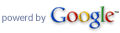
コメントを残す