大学受験の勉強で、長文が苦手な人は多いと思います。読解力をつけるための方法はいろいろあると思いますが、少し時間がある時を見計らって、文と文とを接続することばを一気にまとめてマスターすると、読解がより楽になります。
各種「接続詞」や「接続詞の働きをする言い回し」の、各種使い方を知ることは大事です。
そして、やはり、文をつなぐ働きをする分詞構文や to不定詞などは、早く文を読み解くポイントになります。
高校に入ったら、「接続詞ノート」を作り、テキストやありとあらゆる練習問題やテストに出てくる、「接続部分のフレーズと使い方」をメモし続けていけば、折々に、繰返しそれを見てマスターし、入試の前には、さっと眺めていくと役に立ちます。
同じように、熟語やまとまったフレーズを、「フレーズノート」を作り、整然とメモしていけば、習った熟語を忘れることなく積み重ねられます。
熟語は長文読解では大変重要な役割を果たしています。
それを知らないと文法問題にも影響しますし、長文読解の正解選択肢の中で、紛らわしい仕掛け問題になって出てきたりもします。
熟語は最終的には、まとまった市販の熟語帳を全て覚えましょう。
受ける大学の難易度によって、レベルを選べばいいです。単語帳も同じです。
単語・熟語は受験勉強の定番です。
センター試験には数字や表の読解問題が複数ありますが、これらには、独特の決まった言い回しと単語があります。
表やグラフの内容の何を説明し、何を問うているのかが素早く理解できるように、これらの問題では、過去問題をたくさん解いて、各種類のデータ問題の種類別の単語や言い回しを覚えましょう。
数字や%や割合、方角などの表現の仕方や独特の単語や数字の表現などを覚えておかなくてはなりません。
長文でもかなり長い場合は、後の質問に答える時に、本文のどこを探せばいいのかが、分かりにくくなります。
しかし、たいていは、文の内容の順に質問が出てきます。
全部読んでから答えの選択肢を読んで考えようとすると、どこの部分だったのか分からなくなります。
なので、まずは最初に、1段落と最後の段落を読み、登場人物とその立場、そしてどういう場面でどんな問題が起こったのか、そしてどう解決したのかを、おおまかにざっと掴んで理解します。
その後は、第1問の選択肢の質問をさっと読み、今度は本文の上の一部分を読んでから、選択肢を解答します。
終わったら、2つ目の選択肢をさっと読み、本文の大体のその部分を読んで、選択肢を選びます。特に長い長文を読むときには、一文ずつ訳しながら読むと時間がかかって、最後の問題までたどり着けなかったりします。
普段から、分からない単語にとらわれず、大まかに意味を取りながら読み進み、質問に関係がありそうな部分は、丁寧に訳しながら読むというやり方が効率的です。
ペンネーム:NY
英語レベル:英語教員免許取得者
- 目標:大学受験
- 分野:リーディング(読解力)
- 場所・ツール:単語帳 | 教科書・参考書
- 英語学習法:ボキャビル・語彙増強 | 英文法
- 英語レベル:中級
みんなの英語勉強体験談検索
全体験談数115個
The Japan Times Alpha(ジャパンタイムズアルファ) あらゆるレベルの人に購読をオススメする英字新聞です
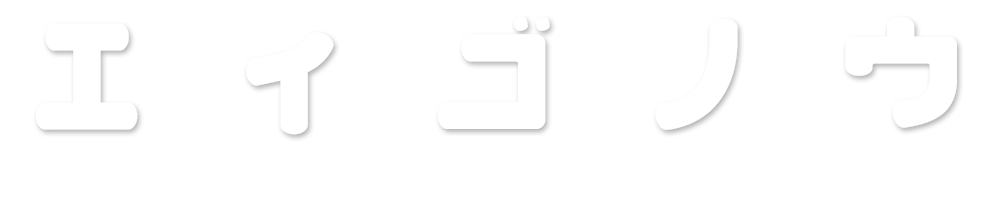



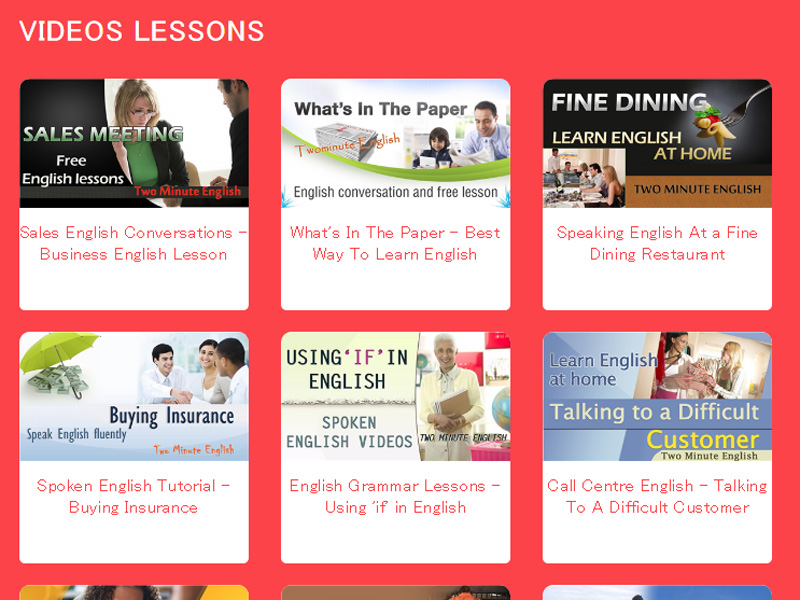

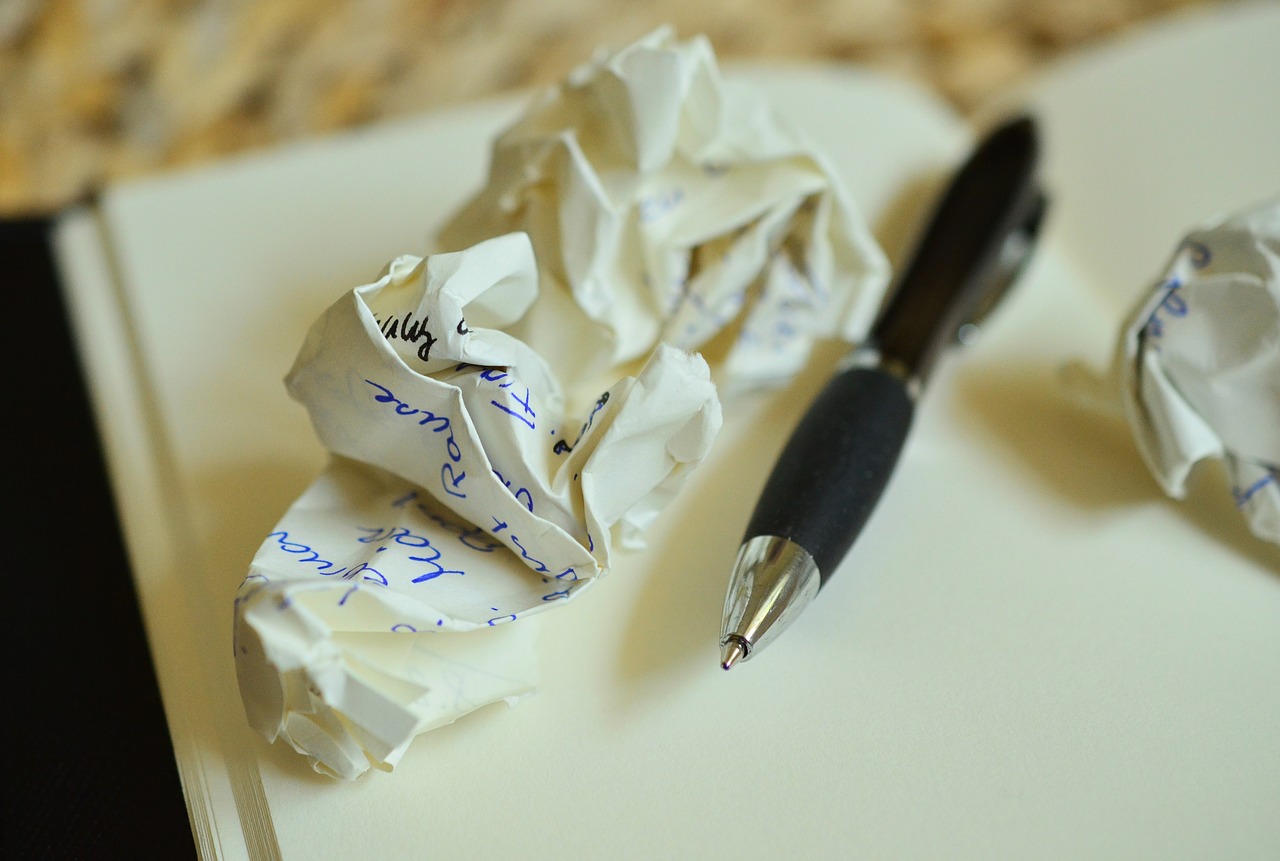

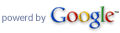
コメントを残す